|
ここで、先ほどの話に戻ります。自分事になるとか、メリットを知るとか、メリットを体感する、では、これをこのステップに置き換えて考えるならば、これ、何かといったら、明確なビジョンなんです。もう一つは、具体化です。
よく、私はいやらしい性格なものですから、会社にいきますと、大体どの会社でもそうなのですが、講堂とか会議室とかに入りますと、「企業理念」が貼ってあるではないですか。企業理念で、例えば、「顧客満足第一主義」などと書いてあったりするわけです。それで、「顧客満足第一主義のためにあなたは何をしていますか」と聞くのです。そうすると、「顧客満足第一主義です」という答えが返ってくるんです。「だから、具体的に何をしていますか」と聞きますと、「いや、いろいろやっています」「じゃ、ほんの一つの例をあげてみてください」というと、結構返ってこないんですね。何かといったら、お題目がお題目のまま終っている会社が多いですね。
話を少し換えます。――決めたことが動かない会社は何かといったら、決め事って、会社が大きくなればなるほど、組織が大きくなればなるほど抽象的になっていきます。抽象的なことを抽象的なまま落し込んでいくから、抽象的にものをとらえて、実際具体化されていません。ですから、腹に落ちるわけがない。
そしてビジョンもそうです。ビジョンも、不明確です。よく聞くんです。売上目標いくらと書いてあるでしょう。まじめな顔をして聞きます。「何のためにやるんですか」と聞きます。皆さん、何と答えます? 皆さんの部下に、私みたいにこんな聞き方する方はいらっしゃらないと思いますが、聞かれたら何と答えますかねという話です。
ここで、答えは何でもいいんですよ。極端な話をすると、別に会社のことでなくてもいいです。自分自身の答えでもいいんです。「おれは、これをやってこうしたいんだ」という思いを語れるかどうかということです。借りてきた知識というのは、皆さん方の心を動かしません。自分の言葉で話してはじめて人は感じるわけです。
まず、理解してもらって納得してもらうこと、そして次に大事なことが、成功イメージです。私、こういう仕事をしていますと、いろいろな方の講演を聞かせていただくことがあります。 明石屋さんまさんの「ホンマでっか!?TV」というのをご覧になったことありますか。あそこに出ている「児玉光雄」さんという、かなり体格の変なおじさんがいるんですけれども、テレビで見ると、ただの変わったおやじなのですが――そんなこと言ったら怒られますね――ちょっと変わったおじさんなんですが、実際にお会いすると、ものすごくクレバーで、すごく熱い方なんですが、その方がこんなことをおっしゃっていました。人間が一番集中力を発揮するときはどんなときか。勝率70%のときだそうです。
これは、科学的な実験をする。例えば目の前に箱を置いて、そこにボールを入れるという行為をしたときに、目の前で確実に入るところだと、もちろん結果としては入りますが、集中力がないそうです。籠の位置を少しずつ遠くに離していきますと、少しずつ難しくなっていきます。難しくなるにあたって、人間というのは自動的に集中力が増していきます。これは理屈抜きです。
皆さん方も経験されています。絶対できるということはたぶん油断しています。集中力ないです。どんどん上がっていって、70%くらいのところが一番集中力が高まるそうです。それより確率が下がってくると、だめでもいいやということが働くのかどうか、集中力が薄れ始めるそうです。そしてある確率以下(難易度)になってくると、人間は、こういう本能が働くそうです。だめなときに傷つきたくないので最初から言い訳をつくっておくという原理です。皆さん方も経験あるはずです。
何をお伝えしたかったか、ちょっと話が逸れてしまいましたが、本気で実行させるためには、成功イメージを持たないとやりません。こんなふうにやればいい、いけそうな気がする。この「気がする」というのが非常に大事なのです。
ただ、これだけでも非常に難しいので、何が必要かというと、厳しさが必要です。成功イメージというのは、本当はこれで自主的に動いてもらうのがベストなわけですが、これがなかなか難しい。となると何が必要になってくるかというと、「いいから、やれ!」という厳しさです。残念ながら、今まで言っている話と百八十度違うと思われるかもしれませんが、この厳しさが必要です。とにかくやらせなければいけないんです。
よくお話をしますが、「激しさと厳しさ」という言い方をします。激しさは必要ありません。激しさというのは、「やれ! とにかくやれ!」といって、声を荒らげたり怖い顔をしたりして動かすやり方です。これは「激しさ」といいます。これは、やってもいいですが、必要ありません。必要なのは、やるまで動かないしつこさです。営業会議なんかでもよくわかるのですが、怖い上司が部下のことを会議の場で罵倒するんです。それで言いすぎたと思うのでしょう、終ったあと、「じゃ、飲みにいこうぜ」といって和気あいあい、ごますりにいくわけです。会議の場でどなりちらしておきながら、そこに対して、どなりちらしたことを、やったか、やらないかを確認しないまま、話題をすり替えているわけです。ケース・バイ・ケースで、言いすぎてしまったかなと思って、すり寄ることを否定していません。でも、万事が万事それなのです。
この状態になると、部下、人は、どうなるでしょう。会議のときに耳を塞いでおけば、時間が過ぎてしまいます。これは結構くせ者です。皆さんの会社のリーダーの中にも、激しいリーダーというのはいると思います。一見怖いです。一見怖いですが、本当はなめられています。なぜかといったら、その場を、その会議なり、その人の前の瞬間だけ通りすぎれば事なきを得ることがわかっている。
でも、活気ある部下の中で成功イメージを持たせることが一番大事なのですが、そうでなければ、ここだけ「or」という言葉を使いました。できなければ、まずはしつこくやらせることです。やらないと何も変わらない。やったあとに出てくるのは何かというと、成長実感というのと継続の仕組みです。
我々は、何か物事をやろうとするときに、継続の仕組み、どうやって続けるかという仕組みづくりについて一生懸命考えます。これが間違っているとは言いません。でも、問題なのは、いくら仕組みをつくっても、エネルギーの源泉が必要です。心のエネルギー。つまり、続けてもいいかなという源泉です。これは何かといったら、成長実感です。成長とか成果というのはこういうふうに考えていただければ結構かなと思います。
私は、この仕事をしていますから、成果を絶対出さなければいけない。要は結果を出さなければいけないという気持ちは常に持っています。結果とは何か、成果とは何か、といったら、相手が求める結果です。
ただ、ここでいう成長実感というのはどういうことかといったら、成果という領域のことではありません。成果というゾーンのことではありません。何がいいたいかというと、成長という傾きです。つまり、目指す方向に対して近づいているのか、近づいていないのかということです。
成果というのは、残念ながら、何度もお話しするように、外的要因に振り回されます。今、非常に強いアゲインストとか増えていますから、必ずしもここ( )にいけるとは限らないのです。何がカケルカというと、我々、ここに達することが目的です。でも、ここでいっている、続けられるか続けられないかというのは、この傾きを、近づいていることを感じさせるかどうかだけです。
でも、多くの場合は、「成果が出なければ意味がないんだよ」という言葉を一言いって、結果的に成果がまったく上がらない組織をつくっているケースです。少しでもいいから近づけるようにしていかなければ――変な話、ゼロサムゲームではないんですよ。少しでも成長していれば、続けるように次があるんです。でも、これを諦めてしまっているケースがあります。ということをよくお話をしています。
ここでいうのは何かというと、成長実感ということは非常に大事なのです。これを語り合える文化かどうかということです。もちろん我々は、企業であって、営利法人であって、業績目標を達成して利益を上げてやっていくことがもちろん最終的なゴールです。でも、それが出ていないからといって、怖い顔してぐいぐいやっていって、出なければ意味がないと突き放していって、先ほどずっとお話ししている時流の中の人間たちを、本当に成果に結びつくのかというと、結びつかないような気がしています。
もちろんある日突然、瞬発的に結びつくことがあるかもしれませんから、絶対に結びつかないということをここで断言することはしません。ただ、活気ある組織にはなかなか結びつかないかなということです。ここをみてあげるということが非常に大事なことなのかなということであります。
皆さま方の会社においてどうでしょうか。結構、見ていますと、続かない、活気が出てこない組織というのは、そもそも決めていないという話もないことはないのですが、仮に決めているとすると、具体性、明確なビジョンがないまま理解させようとして、皆さん方、お利口になってきているので、とりあえず頷いている。でも、動かない。なんでといったら、成長イメージがないからです。成長イメージがないし、では、厳しくやっているかというと、表面上厳しくやっているように見えていたとしても、実は厳しくもなんともなく、ただ単に激しくて、その場しのぎ的な高圧で終っているケース、そして継続の仕組みについては一生懸命考えていますが、そこには成長の仕組みを本気で回すための心のエネルギーといいますか、やりたいと思わせる成長実感が伴わないというか、成長実感を気づいてあげられない。気づかないというか、そこに目を向けない組織。こういう中で活気ある組織に果たして結びつくかどうかということです。
先ほど言いましたように、本当にすごい優秀な方だと、自分自身でこのサイクルを回すことができます。もしかしたら、ここにいらっしゃる方の半分くらいの方は、仕事においてはこのサイクルを自分たちで回してこられた方だと思います。でも、回せない人が増えていて、回せる人だけを採用できて、回せる人だけが自分たちの部下としてやってきている、社員としてやってきているのであれば、それに対して私は何ら――これを自力で回せるのが理想ですからいいとは思うんですけれども、ということでございます。 |
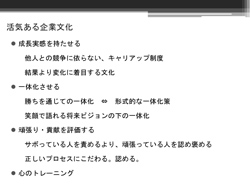 |
| 画像をクリックしてPDFを表示します |
|
活気ある企業文化
では、最後まとめていきたいと思います。
これは、1枚にまとまっていますが、皆さん方につけているものと同じものです。
何度も言いましたが、今どういう時代かというと、成長実感です。成長実感の大事なことは、他人との競争に依らない。自分個人のキャリアアップ実感です。自分自身が伸びている。
それから明確なビジョンでの上下関係です。ノルマ目標ではなくて、笑顔で語れる将来ビジョンの下の
|
|
ものです。
自分の長所を生かしている、貢献している、必要とされている実感です。冒頭に雑談ぽくしたお話で、船井総合研究所、当社の話をしました。なぜ船井総合研究所が成っているかというと、この上に書いてある三つができているからです。できているというか、こういう企業文化を根付かせることに船井幸雄さんは成功したんだと思います。あくまでも"たぶん"ですが。たまたま私のような優秀な社員が偶然集まってしまっただけなのかもしれませんが、そんなことはあり得ないと思います――冗談ですよ。
正しいプロセスにこだわる。認めること。それから頑張り・貢献が評価される。さぼっている人を責めるより、頑張っている人を認め、褒める風潮です。これも先ほどお話ししたことです。マネジメント志向の強い会社は何かというと、できない人をどうやってさせるかということに主眼を置きますから、さぼっていない人をどうしめつけるかということです。
実際にルールというのは、大体こうです。ルールを破るやつは、ルールを厳しくしても、さらに抜け道を探します。ルールを厳しくすると何が起きるかというと、まじめな人が窮屈な思いをするだけで、不真面目な人を取り締まることはまずできません。 |
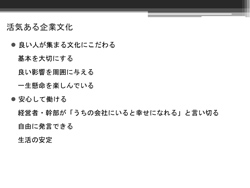 |
| 画像をクリックしてPDFを表示します |
|
活気ある企業文化
それから活気ある企業文化としてお話しするのは、良い人が集まる組織です。良い人が集まる文化にこだわります。良い人というのは良い影響を周囲に与える人です。一生懸命を楽しんでいる人です。それから上司、会社の人間的理解、人間的影響を高める、こういったことが企業の中のポリシーかなということでございます。
「じゃ、どうやって制度に落し込んだらいいんですか」という質問がよくあります。制度の中に落し込む
|
|
ことは可能ですが、最後は結局、運用なんですね。
ちょっと最後にこんな話をして、最後の最後で終わりなんですが、企業組織、企業文化ということで、「COACH(コーチ)」と呼んでいます。とある先生からお聞きしているんですが、comprehension、「理解する」という言葉かな。「包含する」という意味もあるそうですが、訳しますと、「生き方、感情をわかってあげる組織」。人はそれぞれ価値観を持っています。ですから、生き方、感情をわかってあげる。それからoutlook。これは「見通す」というのが直訳なんでしょうけれども、ちょっと意訳かもしれませんが、「結果より変化を見通す」。結果ではなく、ベクトルがどっちを向いているのかということに気づいて、成長実感を教えてあげるという文化です。それからaffection。「愛情で接すること」。これもちょっと意訳ですが。Character、「個性」「行動」とか出てきますが、良いように見せる。そしてhumorです。「楽しませてあげる」。
今の時代に私は徹底的に結果にこだわっていきたいと思います。だから、結果にこだわる。何かといったら、企業成績を伸ばし続けていかなければ実際にハッピーはないと思います。表面的な一体化も意味がないと思います。達成すること、成長することによって初めて一体化できればいいと思っています。だからこそ、先ほどお話ししましたように、遠回りかもしれません、でも、いきなり自分の思う成果を得られる文化、企業状態であれば、それをとっていただければ結構ですが、だめだとすると、今の時流、今の現実を踏まえた上でどうやったら与えられた人的パワーで成長していくということを考えていければ、というふうに思っております。
|
ちょうどお時間になりましたので、ちょっと拙い部分もありましたが、お話しをさせていただきました。
ご清聴ありがとうございました。 |
 |
|
|
