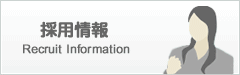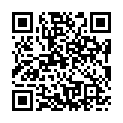トピックス一覧
印刷メディアのエコ効果 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.1
サステナブルな社会に貢献していますデジタル化、情報化の進展に伴い、個別情報をネット上で受発信できる電子メディアが急速に普及しています。いまや、複製と配布を前提とする紙メディアに匹敵するほどの勢いを見せています。そうしたなかで、ペーパーレス時代の到来が往々にして叫ばれることがありますが、果たしてそうでしょうか。エコ意識が高い現代にあっても、紙と印刷は決して地球環境を阻害するものではありません。印刷に使われる紙が、きちっと管理されて森林からつくれたものであれば、資源を無計画に伐採する要因にはなりません。生き生きとした森林は、大量のCO2を吸収し酸素を生み出してくれます。紙は、石油からつくられるプラスチック類と比べるまでもなく、再生可能で生分解性のある優れた素材ということができます。望ましいリサイクルによって継続的に紙が提供されるなら、印刷メディアは電子メディアを上回る環境貢献度を発揮しま...
印刷産業の環境対応早わかり10講
地球環境にやさしい印刷産業を10のトピックスからご紹介いたします。1.印刷メディアのエコ効果 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.12.古紙回収と再生紙 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.23. 再資源化 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.34.大気汚染の防止 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.45.水質汚濁の防止 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.56.CO2削減とCFP制度 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.67.省エネ対策 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.78.グリーン印刷サービスの提供 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.89.グリーンプリンティング認定 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.910.認証制度と環境マーク - 印刷産業の環境対応早わかりNo.10アーカイブに戻る
古紙回収と再生紙 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.2
リサイクル対応型印刷物を製作していきます環境問題に取り組むうえで、資源の有効活用、再生資源の利用はきわめて有効な対策とされていますが、印刷物の素材として欠かせない「紙」に関しても、森林資源の保護や廃棄物削減という観点から、古紙配合率の高い再生紙の採用が進んでいます。日本全体の循環資源の約1割を占めるほど重要な資源となっていますので、製紙業界と印刷業界が力を合わせて古紙利用率の向上に積極的に取り組んでいるところです。古紙には、新聞用紙、印刷・情報用紙などの「紙」向けと、段ボール、紙箱などに使われる「板紙」向けの用途があります。板紙の方が古紙利用率が高いのに対し、紙の場合はそんなに高くありません。それだけに、出版物や商業用印刷物などの使用済みの紙を、再度、印刷・情報用紙のための製紙原料として回収・利用していくことが要請されます。いわば「紙から紙へのリサイクル」です。板紙や段ボールにしか再...
再資源化 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.3
廃棄物の「3R」に全力を注いでいます「循環型社会形成推進基本法」は、廃棄物をすべて循環資源ととらえて発生の抑制と再利用を促すために、廃棄物の処理に関してきちっとした規制を設けています。それは「3R」と呼ばれるキーワードで象徴され、これを遵守してもらうことによって、最終処分量の削減をめざそうというのが狙いです。印刷産業においても、それぞれの印刷会社が「環境自主行動計画」(日本印刷産業連合会策定)のもとで、一定の目標を立てながら最終処分量の削減および再資源化率の向上に協力しています。「3R」とは、①リデュース(最終処分量を減らすために、廃棄物の発生そのものを削減すること)、②リユース(発生した廃棄物のうち、そのまま再使用可能なものは繰り返し使うようにすること)、③リサイクル(再使用できないものを加工処理して、再生資源として使うこと)——を指しています。基本法が定め...
大気汚染の防止 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.4
VOCを発生させない改善策を実行しています大気を汚染する物質としてVOC(揮発性有機化合物)が問題視されています。「大気汚染防止法」では、VOCのことは「大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物」と定義されているのですが、印刷産業では、業界の自主規制によってこのような有害物質の排出抑制に努めるとともに、代替物質への切り替え、除去装置(脱臭装置)の設置などで万全を期しています。印刷産業においてはインキや湿し水、一部の洗浄剤、表面加工剤、製本用接着剤などがこれに関係してきます。印刷インキに含まれるVOCは、すべて印刷後の乾燥工程で蒸発しますので、大気に漏出しないよう排ガス自体を回収処理するのが基本です。オフセット輪転印刷工場やグラビア印刷工場では、悪臭を発する物質が大気に排出されないよう、印刷の際に発生する溶剤や乾燥による排ガスを、触媒や吸着材によって回収もしくは再燃焼...
水質汚濁の防止 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.5
廃液はすべて回収し、きちんと処理しています大気への影響と並んで重視されるのが水質への影響です。印刷産業は、これに関しても「水質汚濁防止法」の規制に従って、有害物質の浄化処理、流出防止に取り組んでいます。印刷工場では、現像廃液、湿し水廃液、洗浄廃液など、製版・刷版・印刷の各工程で発生する全ての廃液を、適切に回収・処理することに気を配っているのです。湿し水を使っておこなうオフセット印刷の場合、印刷機の給水ローラー部と湿し水タンクはクローズドな状態で循環するシステムになっているため、印刷の最中に出る排水は全くありません。環境負荷はないということになります。しかし、長期間使っていると紙粉やインキ成分などでだんだん汚れてくるため、定期的に湿し水を交換しなければいけません。このときに環境負荷が生じるのですが、環境保護を第一義に考え、濾過装置の接続により廃液の循環回収をおこなうとともに、最終的には...
CO2削減とCFP制度 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.6
温暖化防止のために排出量を抑制しています地球温暖化が危惧されるなかで、早急に取り組まなければならないのが低炭素社会の実現です。もっとも効果的な対策は、CO2に代表される温室効果ガスを極力発生させないようにすることです。世界的に定められている削減率を守らなければいけません。そのためには、日常の生活や企業活動を通して、CO2の排出量を減らしていくことが重要です。印刷産業が排出するCO2は全産業のなかでほんのわずかしかないのですが、それでも排出していることに変わりはありませんので、業界あげて具体的な防止対策の実行に邁進し、温暖化防止に努めています。印刷会社における個々の省エネ活動を支援することによって、公約の達成に参画しています。個々の企業がCO2の排出量を削減していくためには、ビジネスの実務面で省エネ対策に取り組むことがもっとも現実的な対応となっています。CO2の削減に取り組む企業姿勢は...
世界の主要な印刷機材展
世界の印刷市場の規模は2014年に7603億ドル(約86.3兆円 1ドル=110円にて)の規模があるといわれており、グローバルベースで見たときには規模の大きい産業です。そのために数多くの大規模な印刷機材展が開催されています。ここでは主要な印刷機材展をご紹介します。IGAS(International Graphic Arts Show) 日本最大の印刷機材展で、drupa(ドイツ)、Print(米国)、IPEX(英国)と合わせて『世界4大印刷機材展』と呼ばれている。 IGAS2015では出展者数345社、入場者数56,533人、出展規模2,688小間の規模を誇る。drupa 世界最大の印刷機材展でドイツのデュッセルドルフにて約2週間にわたり開催される。 drupa2016では出展者数1,828社、入場者数は183カ国から26万人56,533人を数え、展示スペースは15.8万m2。Print...
くらしと印刷
くらしと印刷本章は1994年に発刊された「ぷりんとぴあ: くらしと印刷」を修正・加筆したものです。・A君が抱いた勉強への決意・A君の仕事とメモ・家の中も印刷でいっぱい・木目印刷と立体印刷・Kさんのレクチャー・紙を離れた印刷とは・広がる印刷業の裾野 「A君が抱いた勉強への決意」印刷に関する知識については絶対の自信をもっていたA君でしたが、あるきっかけからその自信はもろくも崩壊。負けずぎらいの彼は、突然「勉強家」に大変身しました。 1. プロローグ印刷会社に勤務するA君は、入社して間もない技術課員。ある日曜日、夕方外出から帰り、テレビのスイッチを入れると、クイズ番組で印刷に関するテーマを扱っていました。<なんてったって、こっちは印刷のプロだよ>と気軽に見始めると、番組ではルネッサンスの3大発明(火薬、羅針盤、印刷)の一つとして印刷を取り上げて、どれが正解か選択形式のクイズを出題しています。本当か...
ちらし広告と印刷 「印刷会社と相談しよう」
「印刷会社と相談しよう」 Cさんは、DTPと言ってもそう簡単ではないとすこし不安になってきました。 事前に印刷会社と打ち合わせておかなければならないことがいろいろあります。1. DTPにもいろいろある相談に行った印刷会社の人に最後に、「一口にDTPと言ってもいろいろな方法があります」 とアドバイスを受け、その詳しい内容を聞くことにしました。パソコンを使ってデザインなどの制作から製版の製造までを行う方法をDTPとまとめて呼ばれていますが、その印刷会社の人の話では、DTPはデザインの進め方、プリンター類の使い方、写真などの画像類の取扱い方、データの完成具合などにより運用方法が異なるらしく、またパソコン自身のOSや使われるアプリケーションソフトとその使い方、バージョンによってもさまざまな問題が起きること、さらに文字にもプロ仕様とアマチュア仕様では異なる部分があるなど、実際にチラシを作る段階になって...
ちらし広告と印刷 「チラシ制作初挑戦—その結果は?」
「チラシ制作初挑戦—その結果は?」 Cさんはいよいよチラシ制作にとりかかりました。 デザインの難しさ、校正の重要性を身をもって体験することになります。1. チラシ制作に取り組む印刷会社の人にいろいろとアドバイスを受けたCさんは、不安もありますが、とりあえず初志貫徹とばかりにDTP制作に取り組むことにしました。 Cさん自身は、パソコンを使うには不自由しないといった自負もありますし、奥さんはデザインに興味があり、自分はデザインセンスがあると普段から言っているので、2人で頑張ればなんとかなるだろうとスタートを切りました。まず、スケジュールです。 チラシを配る日から逆算して、いつから着手すればよいかといったスケジュールを作り、それに沿って着実に進めるつもりでいました。 ところが、自分たちでデザインを始めてみたところ、いろいろな問題がありなかなかうまくいきませんでした。 それでも、Cさんは、奥さ...
ちらし広告と印刷 「デジタルデータを活用しよう」
「デジタルデータを活用しよう」 Cさんのチラシ制作は、回を追うごとに順調になり、効果も出てきました。 しかし情熱はこれで留まることなく、もっと売り上げを伸ばすことはできないかと考えます。1. デジタルデータは保存、再利用に便利チラシ制作を始めて1年。 Cさんのチラシ作りも軌道に乗り、制作の能率もあがってきました。 そんなAさんに、DTPで作られているチラシはデジタルデータとして保存が容易で再利用が可能との情報が入りました。 そこで印刷会社にその点について、話を聞きに行きました。すると印刷会社の人に、使い捨てにしない再利用の方法があるので考えましょうと言われました。 Aさんのお店のチラシに掲載される商品の大半は固定化されていて、新しい種類の商品の割合は多くありません。 そこで毎回使う商品の写真と文字を整理して、再利用する目的を明確にして保存し、簡単に使えるようにしようではないかということになってきました...
ちらし広告と印刷 「チラシはどのようにつくられていくのか」
「チラシはどのようにつくられていくのか」 Cさんはいよいよ印刷会社へ交渉に行きます。 そこで、チラシ作りの工程と、どのような費用がかかるか、アドバイスを受けてきました。1. 印刷会社との交渉さて、いよいよ実践とばかりに、Cさんは同じ町内にある印刷会社に出かけて行きました。 自分でパソコンを使いデザインして作ったデータを印刷会社に持ち込み、DTPでのチラシの印刷を行いたいといった内容の相談です。しかし、その印刷会社は、刷り工程に力を入れているため、パソコンからのデータ出力環境は整えていないとのことで、また刷版に直接出力するCTPとかいうシステムも設置していないようです。印刷会社の人の話では、駅前に大手出力サービスセンターのチェーン店があり、そのサービスセンターではコピーやカラーコピーのサービスから、パソコンデータのプリンターへの出力、印画紙やフィルムへの出力、写真のデジタルデータ化 (画像入力) ...
本づくりと出版印刷 自費出版にチャレンジする
自費出版にチャレンジする 「自費出版」といっても、Tさんにとっては全くの素人です。費用もかかるでしょうし、何よりどのくらいの時間と努力が必要なのか、かいもく見当がつかないのですが、ともかく原稿の作成に取り掛かってみることにしたのです。しかし、何ページにも及ぶ原稿を頭から書き下ろすことなど、プロでもない初心者のTさんには無理なことです。そこで、どのようにして書いたら効率よくまとめることができるかを知りたくて、原稿の上手な書き方についてやさしく解説してある参考書を購入、自分なりにチェックしてみました。そこには、以下のようなことが書かれていました。 きちんとした原稿にすれば、その後の修正作業も最小限で済むので、印刷会社からも大歓迎されるだろうと、Tさんは思ったのです。費用も時間も抑えられるなら、著者にとっても有難いことです。本の構成最初にやらなければいけない、もっとも重要なことは、なぜ出版し...
本づくりと出版印刷 書籍/雑誌のかたちを知る
書籍/雑誌のかたちを知る 原稿の執筆に取り組む傍ら、いずれ印刷を頼むことを前提に、同じ地域にある印刷会社を訪れ、仕事の流れや段取りについて聞いてみることにしました。丁寧に対応してくれた印刷会社から新進気鋭の営業マンNくんを紹介され、ついでに「書籍や雑誌の基本的なかたちを知ることが大切です」といって、本づくりの極意を教えてもらいました。 ページ編集本をつくる場合、書かれている内容と同じくらい重視されるのがページごとのレイアウトです。読者に親しみをもってもらうには、何より可読性が大切なのです。そこでは、どんな書体のどんなサイズの文字を使い、行数と行間、行当たり字数、段数や段間のスペースなどを決めていきます。いわば、どのような組体裁にするかです。最初にNくんから言われたのは「縦組にしますか、それとも横組にしますか? 章や項につける大見出しや中見出し、小見出しはどうしますか? 文字を組版した箇所...
本づくりと出版印刷 出版印刷の基礎知識を学ぶ
出版印刷の基礎知識を学ぶ 原稿の執筆は容易ではありませんでしたが、半年ほどをかけて、ようやく形が見えるところまで漕ぎつけました。完全原稿に向けて何度も読み返し、そのつど、書き直しや追加・削除を繰り返しながら、いよいよ最終段階を迎えようとしています。そうなると、次の気になるのは、印刷や製本を具体的にどうするかです。これらについても、印刷会社のNくんが手持ちの資料を説明しながら丁寧に伝授してくれました。印刷用紙(1)用紙の種類印刷する以上、情報を載せる媒体としての用紙が欠かせません。現在、一般的に印刷用に使われている紙には、薄い洋紙と厚い板紙がありますが、ここでは前者についてご紹介しておきましょう(ちなみに後者は紙器用、パッケージ用に使われます)。モノクロの文字が中心の書籍や雑誌など出版印刷物は、写真が多いカラー刷りのチラシ、カタログ、ポスターなど商業印刷物以上に、用紙が果たす役割は重要と...
本づくりと出版印刷 印刷を発注、出来上がりを待つ
印刷を発注、出来上がりを待つ パソコンに入力してきた原稿がまとまり、そのデータを印刷会社に渡すときがやってきました。細かい打ち合わせをおこなうため、再び印刷会社を訪れて、担当してくれることになった営業マンNくんと改めて会いました。何から自分の希望を伝えたらいいのか、全く分からなかったので、“大船”に乗った気持で相談させてもらうことにしたのです。 実際の打ち合わせTさんからみれば相談、Nくんにすれば営業に当たる打ち合わせをおこなったのでが、何も取り決めをしないで作業をスタートさせると、次の段階ですぐ頓挫してしまいそうです。この打ち合わせは印刷物を製作していくうえで非常に重要なことと考えられますので、それだけにTさんも真剣に取り組みました。(1)仕様の決定最初に発注者であるTさんが、どんな書物をつくりたいのかについての、自分なりの希望をしっかり固めておかなければなりま...
本づくりと出版印刷 「電子出版」の動向を聞く
「電子出版」の動向を聞く 印刷会社に何回か足を運ぶうちに、営業マンのNくんとも親しくなりました。Tさんは、最近のニュースなどで強い関心をもっていた「電子出版」の状況について聞いてみたくなりました。Nくんの紹介で、制作部署に所属するベテラン社員のEさんから、ひと通りの話を聞くことができました。Tさん自身が今すぐ、電子出版に取り組むというわけではないのですが、作成した原稿データをもっている以上、参考として、最近の動向を知っておきたかったのです。TさんとEさんとの間には、以下のような会話が交わされました。 電子書籍の現状・最近、電子書籍が話題となっていますが、どんな状況にあるんですか?「日本では2010年が電子書籍元年といわれましたが、当初は従来の出版概念に捉われていたせいか、立ち上がりが随分鈍かったのです。しかし、その後、携帯電話に加えてスマートフォンやタブレット端末が急速に普及したため、電...
省エネ対策 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.7
会社ぐるみの管理体制で万全を期しています燃料資源の有効利用を確保するための「省エネ法」が制定され、企業に工場、社屋、機械設備等に関わるエネルギー消費の合理化を求めています。省エネ化、つまり電力やガス燃料の使用量を少なくすることによって、CO2の削減を促すという目的があります。印刷工場においても、生産システムの改善、ムダ(歩留り)やロス(不良製品)の排除を通じて、省エネ化に取り組んでいます。工場建屋の空調に配慮するとともに、生産設備の高性能化や稼働率向上をはかることが有効な対応策となりますので、これらの要件を考慮に入れた総合的な気配りを続けています。省エネ対策においてとくに留意しなければいけないのは、単位当たりのエネルギー使用量(原単位)を基準にして管理することです。生産量(印刷の場合は受注量)の増減がエネルギー使用量に影響を与えてしまう弊害を避けなければならないからですが、原単位の低...
グリーン印刷サービスの提供 - 印刷産業の環境対応早わかりNo.8
「グリーン基準」を策定して環境貢献しています循環型社会の実現に向け、リサイクル品や環境負荷の小さい製品、サービスなど、いわゆるグリーン製品を意識的に購入することを促す目的で制定された法律が「グリーン購入法」です。これによって、社会全体でグリーン購入の動きが活発になっていったのですが、印刷産業としても環境配慮への姿勢と方向性を示すべく、業界が提供するオフセット印刷、シール印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、さらには光沢加工の各種サービスについて、自主的な「グリーン基準」を指針として策定しています。企業レベルで環境に配慮した事業活動を積極的に推進すると同時に、印刷産業の社会的責任で環境負荷をより一層低減することが可能になりました。この基準は、現在の印刷関連技術の動向や印刷業界が課題としている環境問題などを踏まえて、①印刷業界がめざすべき方向性、印刷会社として望ましい姿に向けた努力目標、②...