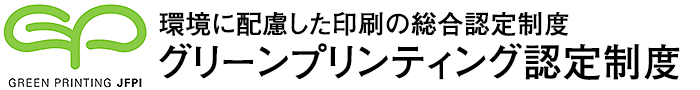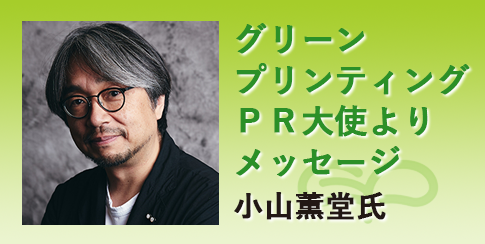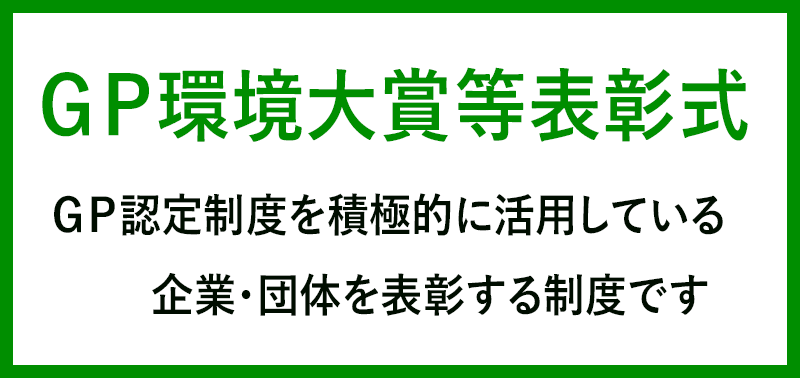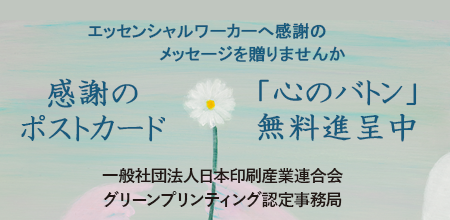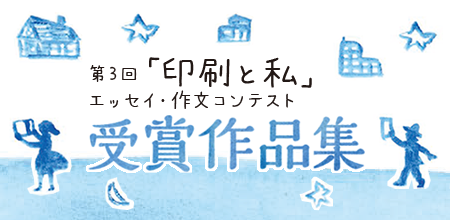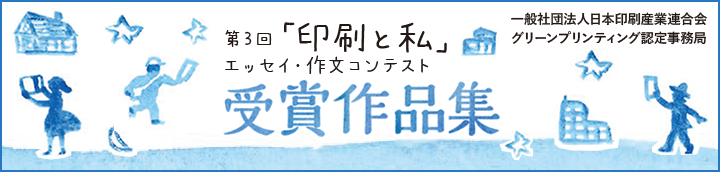
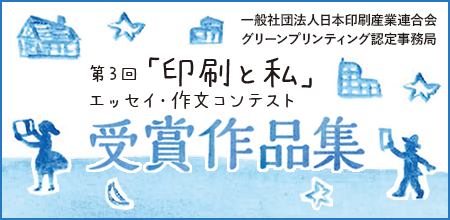
 「印刷と私」コンテスト審査委員会 審査委員長 小山薫堂氏
「印刷と私」コンテスト審査委員会 審査委員長 小山薫堂氏今年も、応募作品を読ませて頂いたことで、たくさんの大切なことに気づかされました。改めて実感したのは、人類が発明した印刷という技術の価値の大きさです。昨今の文字やデザインの大半は、インターネットの画面上だけで完結しています。しかしそれは「存在」というより「表示」。未来に残す確かな文化の足跡にするには、少し不安が残ります。
印刷は人と人をつなぐために生まれ、想いや事実を伝えることで世の中を動かしてきました。そして今もなお、たくさんの人たちが印刷された本を愛し、印刷で再現される色に心を揺さぶられます。
印刷とは、今の想いを未来に渡す心のバトン。これからも一人でも多くの人が印刷と自分の関係を再考することで、印刷文化の灯火が世の中を照らし続けることを祈念しています。
一般の部
「写真撮って、パパ!」
満開の桜トンネル。紺碧の海。赤く燃える紅葉。白銀の雪景色。
どんなに美しい風景を背にして私がねだっても、一眼レフをぶら下げた父はいつも首を横に振ってばかり。
「俺は風景カメラマンだ。人物は撮らない」が常套句。
「一人娘よりも景色の方が大事なの?」幼い頃から私は不満だった。
だから家族旅行に行っても、思春期を迎える頃には父に「写真を撮って」と頼まなくなっていた。
そして、大人になった私は次第に家族と出掛ける事もなくなっていった。
……一年前。三十年間暮らした故郷を遠く離れた地へ私は嫁いだ。
嫁入り前夜、居間で母としんみり語っていると、父が沢山の冊子を抱えて現れた。
「嫁入り道具だ。持っていけ」 照れ隠しなのか無愛想に手渡す父。 一目で手作りと分かる製本。丁寧に綴られた装丁には、全て同じ文字が印字されていた。
『ゆかりの十二ケ月』 唯一違うのは西暦だけ。平成元年から始まり、平成三十年まで一年も欠かさず揃っていた。
驚きながら中を開くと……それは、父手製のオリジナルカレンダーだった。 春夏秋冬、三十年分の十二ケ月の『私』がいた。母と手を繋いで桜並木を歩く入園式の私。祖父と海で西瓜割りをしている小学生の私。中学の体育祭でリレーのアンカーを走る私。旧友とはしゃぐ成人式の振袖姿の私。
そこには、カメラ目線の私は一人もいない。全て父の隠し撮り写真。だからこそ、自然な笑顔。父だから、娘の一番『いい顔』を知っていたのだ。
大きくプリントされた私の写真の下の、カレンダーの日付欄に印字された文字は、「入学式」「運動会」「テニスの試合」「卒業式」「結納」……。
全て私に纏わる行事で埋め尽くされていた。父の愛情に彩られた十二ケ月×三十年。
「なーんだ、風景よりも私の方が大事だったんじゃん」
世界でただ一つだけの手作りカレンダーを抱き締めながら、三十年越しに父の愛情を泣き笑いで痛感した。
「ありがとう、パパ」
満開の桜トンネル。紺碧の海。赤く燃える紅葉。白銀の雪景色。
どんなに美しい風景を背にして私がねだっても、一眼レフをぶら下げた父はいつも首を横に振ってばかり。
「俺は風景カメラマンだ。人物は撮らない」が常套句。
「一人娘よりも景色の方が大事なの?」幼い頃から私は不満だった。
だから家族旅行に行っても、思春期を迎える頃には父に「写真を撮って」と頼まなくなっていた。
そして、大人になった私は次第に家族と出掛ける事もなくなっていった。
……一年前。三十年間暮らした故郷を遠く離れた地へ私は嫁いだ。
嫁入り前夜、居間で母としんみり語っていると、父が沢山の冊子を抱えて現れた。
「嫁入り道具だ。持っていけ」 照れ隠しなのか無愛想に手渡す父。 一目で手作りと分かる製本。丁寧に綴られた装丁には、全て同じ文字が印字されていた。
『ゆかりの十二ケ月』 唯一違うのは西暦だけ。平成元年から始まり、平成三十年まで一年も欠かさず揃っていた。
驚きながら中を開くと……それは、父手製のオリジナルカレンダーだった。 春夏秋冬、三十年分の十二ケ月の『私』がいた。母と手を繋いで桜並木を歩く入園式の私。祖父と海で西瓜割りをしている小学生の私。中学の体育祭でリレーのアンカーを走る私。旧友とはしゃぐ成人式の振袖姿の私。
そこには、カメラ目線の私は一人もいない。全て父の隠し撮り写真。だからこそ、自然な笑顔。父だから、娘の一番『いい顔』を知っていたのだ。
大きくプリントされた私の写真の下の、カレンダーの日付欄に印字された文字は、「入学式」「運動会」「テニスの試合」「卒業式」「結納」……。
全て私に纏わる行事で埋め尽くされていた。父の愛情に彩られた十二ケ月×三十年。
「なーんだ、風景よりも私の方が大事だったんじゃん」
世界でただ一つだけの手作りカレンダーを抱き締めながら、三十年越しに父の愛情を泣き笑いで痛感した。
「ありがとう、パパ」
父は六十歳の夏、原爆病で亡くなった。広島で生まれ育ち、戦争で家族や親戚、多くの友人を失っている。壮絶な経験だったはずだが、生前、当時のことはほとんど語らなかった。封印したい過去なのだろうと、あえて聞かずにいたが、父の遺品を整理していて驚いた。遺された本のほとんどが戦争に関連するものだったのだ。ページをめくると、ところどころに線が引かれている。
父は孤独な人だった。毎晩のように一人で酒を飲み、酔っては軍歌を歌い癇癪を起こす。私はそんな父がいやで、親しく会話をした記憶がほとんどない。父のことはわからずじまいだったが、「線」を見ているうちに、いろいろな「父」が想像された。
「生き残っても地獄だぜ」という特攻隊員の言葉に引かれていた線。それはまさに父の気持ちだったのかもしれない。被爆してから最期まで入退院の繰り返しだった父、以前は野球少年だったと聞く。人生、こんなはずではなかったと何度ため息をついたことだろう。 ある短い線に目が留まった。配給の「汁粉」に引かれていた一本。母の作る汁粉をうれしそうに食べていた父の顔が浮かんだ。そのときばかりは穏やかな優しい目をしていた。父は何を思って、ここに線を引いたのか。
戦争さえなければ父の生き方は大きく違っていたはずだ。ふと、父は戦争を封印したかったのではなく消化したかったのではないかと思った。だから戦争に関する本を読み、線を引きながら本と対話していたのではないだろうかと。理路整然と並んでいる活字の横に、鉛筆で引かれた手書きの一本が妙に生々しく感じられた。
自分の経験や思いを直接、話すには重すぎたのかもしれない。わかってもらえないと諦めていたのかもしれない。でも、本は万人に向けて書かれたもの。父はその客観性に心を開いていたのかもしれない。
遺された本を読みながら、私は父が引いた線と会話する。父は「戦争」をどこまで消化できたのだろうか。
父は孤独な人だった。毎晩のように一人で酒を飲み、酔っては軍歌を歌い癇癪を起こす。私はそんな父がいやで、親しく会話をした記憶がほとんどない。父のことはわからずじまいだったが、「線」を見ているうちに、いろいろな「父」が想像された。
「生き残っても地獄だぜ」という特攻隊員の言葉に引かれていた線。それはまさに父の気持ちだったのかもしれない。被爆してから最期まで入退院の繰り返しだった父、以前は野球少年だったと聞く。人生、こんなはずではなかったと何度ため息をついたことだろう。 ある短い線に目が留まった。配給の「汁粉」に引かれていた一本。母の作る汁粉をうれしそうに食べていた父の顔が浮かんだ。そのときばかりは穏やかな優しい目をしていた。父は何を思って、ここに線を引いたのか。
戦争さえなければ父の生き方は大きく違っていたはずだ。ふと、父は戦争を封印したかったのではなく消化したかったのではないかと思った。だから戦争に関する本を読み、線を引きながら本と対話していたのではないだろうかと。理路整然と並んでいる活字の横に、鉛筆で引かれた手書きの一本が妙に生々しく感じられた。
自分の経験や思いを直接、話すには重すぎたのかもしれない。わかってもらえないと諦めていたのかもしれない。でも、本は万人に向けて書かれたもの。父はその客観性に心を開いていたのかもしれない。
遺された本を読みながら、私は父が引いた線と会話する。父は「戦争」をどこまで消化できたのだろうか。
ここに約四十年前、私が初めて買った本がある。女児向けのギャグ漫画だ。
漫画の主人公は、あさりという小学四年の女の子。彼女を中心に、ドタバタギャグが繰り広げられる。因みに三十五年に渡り某誌の看板となったロングラン作品だ。
初めてあさりのコミックを買ったとき、私はまだ幼稚園児であった。当然、あさりは私にとってお姉さんということになる。が、この漫画の登場人物は歳を取らない。数年後に「やった~、あさりと同い年だ~」と喜んだのも束の間。私はあっという間に彼女を追い越し、気づけばあさりの母親より年長者になっていた。あの日の幼稚園児が、今では堂々たる中年である。
大人になった今でも、私は時々あさりを読み返す。全百巻なので時間はかかるが、あさりとの時間はいつだって楽しい。
本棚にズラリ百冊並んだあさりを見て思う。やはり最初の頃のものは劣化が激しい。子供の時分に買ったものなので管理が悪かったというのもある。しかし、やはり四十年も経っているものだ。紙に印刷をして作った本は、どんなに気をつけて保存しても必ず劣化する。紙は黄ばむし手垢はつく。ページも微妙に波打っていて、微かだが、不思議な匂いもする。つまり、生きているということだ。
同じ年月を過ごし、私は歳を取ったが、あさりは小学生のままだ。けれど本は、ちゃんと私と一緒に歳を取っている。そんな本に私は話しかけるのだ。「お互い老けたのう」と。学生の頃から仲良くしている友人に語りかけるように。
この先も、私は紙の本を買い続けるだろう。デジタルは確かに便利だ。百冊分の物語を簡単に、どこにだって持ち運べるし、何年経ってもきれいなまま。だけど、それでは何だかさみしい。
私も本も、時間をかけてゆっくりとバアサンになっていく。そんな紙の本を私はこれからもそばに置き、人生の最後まで、ゆっくりと同じ時間を過ごしたいと思う。
漫画の主人公は、あさりという小学四年の女の子。彼女を中心に、ドタバタギャグが繰り広げられる。因みに三十五年に渡り某誌の看板となったロングラン作品だ。
初めてあさりのコミックを買ったとき、私はまだ幼稚園児であった。当然、あさりは私にとってお姉さんということになる。が、この漫画の登場人物は歳を取らない。数年後に「やった~、あさりと同い年だ~」と喜んだのも束の間。私はあっという間に彼女を追い越し、気づけばあさりの母親より年長者になっていた。あの日の幼稚園児が、今では堂々たる中年である。
大人になった今でも、私は時々あさりを読み返す。全百巻なので時間はかかるが、あさりとの時間はいつだって楽しい。
本棚にズラリ百冊並んだあさりを見て思う。やはり最初の頃のものは劣化が激しい。子供の時分に買ったものなので管理が悪かったというのもある。しかし、やはり四十年も経っているものだ。紙に印刷をして作った本は、どんなに気をつけて保存しても必ず劣化する。紙は黄ばむし手垢はつく。ページも微妙に波打っていて、微かだが、不思議な匂いもする。つまり、生きているということだ。
同じ年月を過ごし、私は歳を取ったが、あさりは小学生のままだ。けれど本は、ちゃんと私と一緒に歳を取っている。そんな本に私は話しかけるのだ。「お互い老けたのう」と。学生の頃から仲良くしている友人に語りかけるように。
この先も、私は紙の本を買い続けるだろう。デジタルは確かに便利だ。百冊分の物語を簡単に、どこにだって持ち運べるし、何年経ってもきれいなまま。だけど、それでは何だかさみしい。
私も本も、時間をかけてゆっくりとバアサンになっていく。そんな紙の本を私はこれからもそばに置き、人生の最後まで、ゆっくりと同じ時間を過ごしたいと思う。
印刷会社に勤める父は私の卒業文集を開いて飾っている。そこに書かれていたのは将来の夢だった。それをどんな思いで飾っていたかはわからない。
私が初めて六年生の学級担任をしたときのこと。卒業文集を作ることになった。印刷会社も決まったがひとつだけ気がかりなことがあった。それはクラスに一人だけ、不登校の児童がいたことだ。不登校になり、かれこれ四年。何度も家庭訪問をした。部屋で宿題もみた。電話口で歌ったこともあった。泣けば励まし、笑えば一緒に大笑いした。こうして徐々に会話が増え、笑顔も増えた。だけど教室にその姿を見せることはなかった。そして入稿期日の一月三十一日。やはりその一枚が揃わない。印刷会社にかけあった。
「待ってもらえないだろうか」
「この時期は混み合っているからそれ以上はちょっと」 泣く泣く電話を切った。期日を過ぎ、別の印刷会社を探した。その間、彼からなんとか一枚原稿をもらえた。だけど心は複雑だった。そんなとき父から電話がかかってきた。
「おい、うちならまだできるぞ」
藁をもすがる思いで向かった。父は夜な夜な機械をまわした。どうか、どうかできますように。私は手を合わせた。それはわが子に祈りを捧げる親のような気持ちだった。 印刷機を飛び出す一枚一枚。それをじっと見つめる私。そんな私を見つめる父。
「お前も一人前になったなあ」
ぼそっと嬉しそうに言った。
こうして卒業前日、私はできたての文集を手に取った。ふと彼のページを開く。
「先生みたいな先生になりたい」
目頭が熱くなった。何度も書いては消した跡。その筆跡を見て知ってゆく。彼のやさしさ。まじめさ。そして強さ。思わず見開きで部屋に飾った。彼はどんな大人になるのだろう。少しの不安とちょっとの期待。だけど猛烈にワクワクする自分がいた。そうか。印刷っていうのは夢を刷ることなのかもしれない。父の気持ちがわかって少しくすぐったかった。
私が初めて六年生の学級担任をしたときのこと。卒業文集を作ることになった。印刷会社も決まったがひとつだけ気がかりなことがあった。それはクラスに一人だけ、不登校の児童がいたことだ。不登校になり、かれこれ四年。何度も家庭訪問をした。部屋で宿題もみた。電話口で歌ったこともあった。泣けば励まし、笑えば一緒に大笑いした。こうして徐々に会話が増え、笑顔も増えた。だけど教室にその姿を見せることはなかった。そして入稿期日の一月三十一日。やはりその一枚が揃わない。印刷会社にかけあった。
「待ってもらえないだろうか」
「この時期は混み合っているからそれ以上はちょっと」 泣く泣く電話を切った。期日を過ぎ、別の印刷会社を探した。その間、彼からなんとか一枚原稿をもらえた。だけど心は複雑だった。そんなとき父から電話がかかってきた。
「おい、うちならまだできるぞ」
藁をもすがる思いで向かった。父は夜な夜な機械をまわした。どうか、どうかできますように。私は手を合わせた。それはわが子に祈りを捧げる親のような気持ちだった。 印刷機を飛び出す一枚一枚。それをじっと見つめる私。そんな私を見つめる父。
「お前も一人前になったなあ」
ぼそっと嬉しそうに言った。
こうして卒業前日、私はできたての文集を手に取った。ふと彼のページを開く。
「先生みたいな先生になりたい」
目頭が熱くなった。何度も書いては消した跡。その筆跡を見て知ってゆく。彼のやさしさ。まじめさ。そして強さ。思わず見開きで部屋に飾った。彼はどんな大人になるのだろう。少しの不安とちょっとの期待。だけど猛烈にワクワクする自分がいた。そうか。印刷っていうのは夢を刷ることなのかもしれない。父の気持ちがわかって少しくすぐったかった。
「先生、これは何でしょう?」
中国ハルビン市の大学で日本語を教えるわたしに、二年生の女子学生が文学全集の一冊を差し出して言った。見ると本の裏表紙の見返しに端正な文字で、
「一九六四年十一月十日 旭川○○堂にて求む」という言葉と、「○○高校三年」、そして女生徒の名前がしたためられている。
女子学生は私が推薦した井上靖の小説を読もうと大学の図書室でその本を見つけ、驚くほど丁寧に読み込んだ後、書き込みに気づいたのだという。わたしは本を受け取って心地よい手触りと重さを楽しみながら、日本にはこのような習慣を持つ人がいること、旭川は寒さの厳しい北海道の街であること、奇しくも著者の出生地でもあることなどを説明した。 彼女と話しているうちに、その本に印刷されたなつかしい文字の間から半世紀前の肌寒い秋の日に書店でこの本を買い求めた女生徒の姿が細部までくっきりと浮かび上がってきた。街の文化基地だった書店。財布の中身と値段を見比べながら真剣に本を選んだ幸せな時間。大切に持ち帰った本のページをめくる時の小気味よい紙の手触り。そして何よりも清々しいインクの匂い。それは何十年か前のわたしの姿そのままである。
この本は女生徒の手から一体何人の手を経てこの地の図書室へたどり着いたのだろう。想像すると人の一生をなぞらえるかのようだ。この本が海をわたりいま中国の大学生に読まれているなどとは女生徒は夢にも思っていないだろう。印刷された本にはもうひとつの物語がある。
女子学生も私の説明を聞いて、まだ見ぬ日本で五十年前にひとりの女学生が大切に読んだ本をいま中国で自分が手に取っていることに何がしかの感慨を持った らしく、「この女の人はいま七十歳位ですね」と言った。
しかしわたしの心の中の女生徒はいつまでもインクの香りを漂わせた高校三年生のままである。そして本は、印刷された本だけが、時空を超えて人から人へ受け継がれていく。
中国ハルビン市の大学で日本語を教えるわたしに、二年生の女子学生が文学全集の一冊を差し出して言った。見ると本の裏表紙の見返しに端正な文字で、
「一九六四年十一月十日 旭川○○堂にて求む」という言葉と、「○○高校三年」、そして女生徒の名前がしたためられている。
女子学生は私が推薦した井上靖の小説を読もうと大学の図書室でその本を見つけ、驚くほど丁寧に読み込んだ後、書き込みに気づいたのだという。わたしは本を受け取って心地よい手触りと重さを楽しみながら、日本にはこのような習慣を持つ人がいること、旭川は寒さの厳しい北海道の街であること、奇しくも著者の出生地でもあることなどを説明した。 彼女と話しているうちに、その本に印刷されたなつかしい文字の間から半世紀前の肌寒い秋の日に書店でこの本を買い求めた女生徒の姿が細部までくっきりと浮かび上がってきた。街の文化基地だった書店。財布の中身と値段を見比べながら真剣に本を選んだ幸せな時間。大切に持ち帰った本のページをめくる時の小気味よい紙の手触り。そして何よりも清々しいインクの匂い。それは何十年か前のわたしの姿そのままである。
この本は女生徒の手から一体何人の手を経てこの地の図書室へたどり着いたのだろう。想像すると人の一生をなぞらえるかのようだ。この本が海をわたりいま中国の大学生に読まれているなどとは女生徒は夢にも思っていないだろう。印刷された本にはもうひとつの物語がある。
女子学生も私の説明を聞いて、まだ見ぬ日本で五十年前にひとりの女学生が大切に読んだ本をいま中国で自分が手に取っていることに何がしかの感慨を持った らしく、「この女の人はいま七十歳位ですね」と言った。
しかしわたしの心の中の女生徒はいつまでもインクの香りを漂わせた高校三年生のままである。そして本は、印刷された本だけが、時空を超えて人から人へ受け継がれていく。
机の一番上の棚に、ひっそりと佇む一冊の赤い辞書。最近、この位置に移動してきた。今でも覚えている。この辞書との出会いを。
私が小学一年生のとき。いつものように本棚から本を取り出そうとすると、一冊の本が目に留まった。深い赤色の表紙。手に取ってみると、ずっしりと重さが伝わってきた。勝手に開いてもいいだろうか。迷う気持ちもあったが、それよりも正体を知りたいという好奇心が先走った。隅から隅まで文字で埋め尽くされた薄い紙。英和辞書だった。辞書をめくるときに頬を伝う風が心地よかった。
「その辞書はね、ママが高校生のころから使っていたもので、結婚するときに持ってきたの。使っていいよ」と母は言った。
辞書を引いたら必ず、その言葉の横に正の字を書いていた母。単語を調べると、たまにその正の字に出会う。お母さんも引いたんだ。そう思うと、私ももっと頑張ろうという気持ちになる。落書きや色が塗られたイラストに遭遇することもある。母のお茶目な一面を垣間見ることが出来た気がして毎回嬉しい。
辞書は言葉の世界、そして表現の幅を広げてくれる。私の机には他にも四冊の辞書が並んでいるが、赤い辞書の持つ魅力と存在感はどの辞書よりも大きい。InternetもCell phoneも載っていない赤い辞書。使う機会がめっきり減ってしまい、引き出しにしまっていた。
再び手に取るきっかけとなったのは、母の死だった。七年間の闘病生活を経て、昨年の九月、天国へと旅立った。もう、母はいない。会うことも、話すこともできない。
でも、この辞書をめくっていると、母に会えたような不思議な感覚になる。
私が今使っている深い青色の辞書もいつか、自分の子どもに渡したい。もっともっと使って、正の字でいっぱいにして。結婚するときには持って行って、本棚の隅に立てかけておこう。母のように。
私が小学一年生のとき。いつものように本棚から本を取り出そうとすると、一冊の本が目に留まった。深い赤色の表紙。手に取ってみると、ずっしりと重さが伝わってきた。勝手に開いてもいいだろうか。迷う気持ちもあったが、それよりも正体を知りたいという好奇心が先走った。隅から隅まで文字で埋め尽くされた薄い紙。英和辞書だった。辞書をめくるときに頬を伝う風が心地よかった。
「その辞書はね、ママが高校生のころから使っていたもので、結婚するときに持ってきたの。使っていいよ」と母は言った。
辞書を引いたら必ず、その言葉の横に正の字を書いていた母。単語を調べると、たまにその正の字に出会う。お母さんも引いたんだ。そう思うと、私ももっと頑張ろうという気持ちになる。落書きや色が塗られたイラストに遭遇することもある。母のお茶目な一面を垣間見ることが出来た気がして毎回嬉しい。
辞書は言葉の世界、そして表現の幅を広げてくれる。私の机には他にも四冊の辞書が並んでいるが、赤い辞書の持つ魅力と存在感はどの辞書よりも大きい。InternetもCell phoneも載っていない赤い辞書。使う機会がめっきり減ってしまい、引き出しにしまっていた。
再び手に取るきっかけとなったのは、母の死だった。七年間の闘病生活を経て、昨年の九月、天国へと旅立った。もう、母はいない。会うことも、話すこともできない。
でも、この辞書をめくっていると、母に会えたような不思議な感覚になる。
私が今使っている深い青色の辞書もいつか、自分の子どもに渡したい。もっともっと使って、正の字でいっぱいにして。結婚するときには持って行って、本棚の隅に立てかけておこう。母のように。
家の中に、印刷の新しいインクの匂いがするようになった日から、母の顔を覆っていた厚いカーテンが少しずつ開かれ、優しい光のような母の笑顔が戻ってきた。
今から四十五年ほど前、私が中学生の時の事だった。母は長年うつ病を患い、自宅にひきこもっていた。母の笑顔がなくなった家は、本当に暗かった。そんなある日、突然、パートに行くと母は私に告げた。勤務先を聞くと近くの小さな印刷所だと言った。印刷所、ああ、だから母は勤める勇気が出たのだと思った。母は、文字や色彩にとても敏感だった。それに囲まれた仕事に就きたかったそうだが家の事情で好きな道に進めなかったらしい。
パート初日、新しいインクの匂いをお土産に帰宅した母は、職場の様子を嬉々として私に教えてくれた。まるで楽しい遠足から帰ってきた子供のように。それは毎日続いた。たとえば「今日ね、タンポポの写真入りのカレンダーを印刷したんだよ。沢山のタンポポの花が印刷口から出てきて、ああ、もうすぐ沢山の家の中にタンポポの花が咲くんだなあって、ワクワクしたよ」とか。昔、母自身が励まされた言葉が掲載された冊子が印刷された時は、「あの言葉で私のように救われる人がいたらいいなあ」と、優しい目をしてつぶやいていた。そして、母のうつ病はどんどん良くなっていった。
人とコミュニケーションをとることができなかった母だが、信頼していた文字や文章、明るさをくれた色彩を、印刷という仕事を介して沢山の人々に届けることで、母は沢山の人々とつながることができたのだと思う。そして母は明るさを、笑顔をとりもどすことができたのだと思う。
今から四十五年ほど前、私が中学生の時の事だった。母は長年うつ病を患い、自宅にひきこもっていた。母の笑顔がなくなった家は、本当に暗かった。そんなある日、突然、パートに行くと母は私に告げた。勤務先を聞くと近くの小さな印刷所だと言った。印刷所、ああ、だから母は勤める勇気が出たのだと思った。母は、文字や色彩にとても敏感だった。それに囲まれた仕事に就きたかったそうだが家の事情で好きな道に進めなかったらしい。
パート初日、新しいインクの匂いをお土産に帰宅した母は、職場の様子を嬉々として私に教えてくれた。まるで楽しい遠足から帰ってきた子供のように。それは毎日続いた。たとえば「今日ね、タンポポの写真入りのカレンダーを印刷したんだよ。沢山のタンポポの花が印刷口から出てきて、ああ、もうすぐ沢山の家の中にタンポポの花が咲くんだなあって、ワクワクしたよ」とか。昔、母自身が励まされた言葉が掲載された冊子が印刷された時は、「あの言葉で私のように救われる人がいたらいいなあ」と、優しい目をしてつぶやいていた。そして、母のうつ病はどんどん良くなっていった。
人とコミュニケーションをとることができなかった母だが、信頼していた文字や文章、明るさをくれた色彩を、印刷という仕事を介して沢山の人々に届けることで、母は沢山の人々とつながることができたのだと思う。そして母は明るさを、笑顔をとりもどすことができたのだと思う。
私の祖父は印刷業を営んでいました。祖父の家は地下一階に印刷の機械が置いてあり、地上一階は受付、二階は住居があります。私が小さい頃、祖父の家に行くと嬉しそうに私を抱っこして地下に連れて行ってくれました。降りてみると五~六人の従業員さんが忙しく働いていて、印刷の機械の油とインクの匂いが部屋の中に充満していました。
小学生の頃、祖父に私の名刺を作って欲しいと頼んだことがあります。祖父から自分で活字を拾って組むように言われ、お休みの日に自分の名前を組むことにしました。
たった四文字なのに探し出せない、思うようにならないことにイライラしながら、ようやく完成させた時には「できたよー」と地下室から大声をあげました。祖父は完成させたことを褒めてくれ、活字を組むことがとても大変なこと、 印刷機は動かし続けないと使いモノにならなくなること、そのためには日頃から大事に取り扱い、翌日もきちんと使えるように整備をしておかないといけないと話しながら、私の名刺を印刷してくれました。初めての自分の名刺の香りや手触りを今でも覚えています。 祖父の印刷工場では、主に地元商店のちらしや、役場に関する印刷物を取り扱っていました。しかし祖母が亡くなり、祖父も脳梗塞を患い、印刷工場は廃業しました。祖父は施設に入り、私と母は年に数回、誰もいなくなった印刷会社に掃除に帰ります。地下室はインクと油の匂いがして、印刷の機械も時が止まったようにそのままです。その後、祖父は亡くなりましたが、「印刷機は動かし続けなければ使いモノにならなくなってしまう」という声が聞こえてくるようでした。
去年の冬、母の元に、地域おこし協力隊員の方から活版印刷をしたいと要望がありました。あの手触りを懐かしいと思う人たちがいて、復活を望んでいるそうです。祖父も、きっと天国で再び印刷機が動くことを喜んでくれると思います。
小学生の頃、祖父に私の名刺を作って欲しいと頼んだことがあります。祖父から自分で活字を拾って組むように言われ、お休みの日に自分の名前を組むことにしました。
たった四文字なのに探し出せない、思うようにならないことにイライラしながら、ようやく完成させた時には「できたよー」と地下室から大声をあげました。祖父は完成させたことを褒めてくれ、活字を組むことがとても大変なこと、 印刷機は動かし続けないと使いモノにならなくなること、そのためには日頃から大事に取り扱い、翌日もきちんと使えるように整備をしておかないといけないと話しながら、私の名刺を印刷してくれました。初めての自分の名刺の香りや手触りを今でも覚えています。 祖父の印刷工場では、主に地元商店のちらしや、役場に関する印刷物を取り扱っていました。しかし祖母が亡くなり、祖父も脳梗塞を患い、印刷工場は廃業しました。祖父は施設に入り、私と母は年に数回、誰もいなくなった印刷会社に掃除に帰ります。地下室はインクと油の匂いがして、印刷の機械も時が止まったようにそのままです。その後、祖父は亡くなりましたが、「印刷機は動かし続けなければ使いモノにならなくなってしまう」という声が聞こえてくるようでした。
去年の冬、母の元に、地域おこし協力隊員の方から活版印刷をしたいと要望がありました。あの手触りを懐かしいと思う人たちがいて、復活を望んでいるそうです。祖父も、きっと天国で再び印刷機が動くことを喜んでくれると思います。
その日、子供たちは何時間も前から待ち続けていた。「届くのは夕方だよ」。そう言っても、土曜日は学校が休み。お昼を過ぎると、子供たちが集まり出し、今か今かとその時が来るのを待っていた。
「こんにちは。お世話になっています」。来た。印刷屋のおじさんだ。茶色い紙の束をいくつも重そうに抱えている。「待ち切れなかったようで……」。そう言って、一束を先にもらい、子供たちのところに持っていくと、すぐに人だかりができた。
たくさんの視線を浴びながら、ていねいに袋を開けると、その中からは、子供たちが半年をかけてつくった『ふるさと伝説マップ』が姿を現した。「わぁー」という歓声が上がり、一枚ずつそれを手に取った。それからしばらくは無言の時が流れた。みんな夢中でマップを見ている。自分が書いたところを何度も読み返し、印刷された自分の名前を指でなぞる。 そんな子供たちを見ながら、僕はそのマップが完成するまでの日々を振り返った。それは、ふるさと塾というボランティア活動で、中学生の参加者を募って地域の歴史や文化を調べる。その年は、地域に語り継がれてきた伝説を調べ、地図にまとめることになり、地図の製作費用は、ある財団が負担してくれて、地元の印刷会社に頼んで、立派なものをつくることができた。
調査はもちろん、原稿執筆、写真撮影も子供たちが担当し、校正は五回もした。出来上がったマップは子供たちの努力の結晶である。
マップが完成した三年後。東日本大震災と原発事故が起きた。マップに記した場所の中には、放射線量が高くて立ち入ることができない場所もできた。それでもマップには、今もその場所の記憶がしっかりと刻まれている。印刷されたものは、いつまでも手元に残り、次代に引き継ぐことができる。いつかまた役立つ時が来る、はずだ。子供たちは印刷という営みを通して貴重な記録を未来に残したのだ。
「こんにちは。お世話になっています」。来た。印刷屋のおじさんだ。茶色い紙の束をいくつも重そうに抱えている。「待ち切れなかったようで……」。そう言って、一束を先にもらい、子供たちのところに持っていくと、すぐに人だかりができた。
たくさんの視線を浴びながら、ていねいに袋を開けると、その中からは、子供たちが半年をかけてつくった『ふるさと伝説マップ』が姿を現した。「わぁー」という歓声が上がり、一枚ずつそれを手に取った。それからしばらくは無言の時が流れた。みんな夢中でマップを見ている。自分が書いたところを何度も読み返し、印刷された自分の名前を指でなぞる。 そんな子供たちを見ながら、僕はそのマップが完成するまでの日々を振り返った。それは、ふるさと塾というボランティア活動で、中学生の参加者を募って地域の歴史や文化を調べる。その年は、地域に語り継がれてきた伝説を調べ、地図にまとめることになり、地図の製作費用は、ある財団が負担してくれて、地元の印刷会社に頼んで、立派なものをつくることができた。
調査はもちろん、原稿執筆、写真撮影も子供たちが担当し、校正は五回もした。出来上がったマップは子供たちの努力の結晶である。
マップが完成した三年後。東日本大震災と原発事故が起きた。マップに記した場所の中には、放射線量が高くて立ち入ることができない場所もできた。それでもマップには、今もその場所の記憶がしっかりと刻まれている。印刷されたものは、いつまでも手元に残り、次代に引き継ぐことができる。いつかまた役立つ時が来る、はずだ。子供たちは印刷という営みを通して貴重な記録を未来に残したのだ。
「大丈夫、中学生活好きに描いていいから」
何故か、学校文集の表紙を任せられた。それ、印刷して全校生徒に配るやつじゃん。大丈夫って……確かに私は美術部。でも幽霊部員ですよ。運動部は部費が高いからやめてと母に頼まれ、なんとなく入部しただけの私ですよ。
仕方なく、久々にスケッチブックを開く。真っ白い用紙をどんなに眺めても、真っ白い。不毛な私の中学生活と一緒だ。
中学生活……恋とか、部活とか?文化部で応援した野球部の試合が蘇る。私に気づいてマウンドから手を振ってくれたユニフォーム姿のクラスメイトが妙に格好良かった。あの悔し泣きは三年間頑張った証で、頭を下げた彼らの泥だらけのスパイクが印象的だった。 部活、描いてみようかな。私のしなかった青春を。本当はしたかった青春を。
バレー部のアタック、陸上部の高飛び、テニス部がラケットを振って、サッカー部がシュートを決める。様々な部活を見て回り、スポーツ関連の図書も参考にして鉛筆で描いていく。絵の中心部は決まっていた。
「野球のスパイクを一週間貸してくれない?」
頼んだ相手は、あの時私に手を振ってくれたクラスメイト、の隣にいた、ずっと好きだった人。緊張で声を上ずらせて、心臓を爆つかせて、中学生活最大の勇気を出した。彼の真っ黒なスパイクを家に持ち帰り、ちょっとニヤけつつ、泥、汚れ、ほつれのすみずみまで丁寧に再現した。
刷り上がった文集の冊子に、感動してしまった。鉛筆の風合いが白黒印刷に生きている。薄橙色の表紙ぴったりに縮小して印刷されると、スケッチブックの原版とは別物に見えた。つんと印刷したての匂いがした。
「この中学校が続く限り職員室に保管されるんだよ。君は一世一代の大仕事をやり遂げたね」
先生の大げさな言葉が嬉しかった。
あれから二十数年。年季の入った文集の表紙には、甘酸っぱくて気恥ずかしい、私の青い春が今でもくっきり刷られている。
何故か、学校文集の表紙を任せられた。それ、印刷して全校生徒に配るやつじゃん。大丈夫って……確かに私は美術部。でも幽霊部員ですよ。運動部は部費が高いからやめてと母に頼まれ、なんとなく入部しただけの私ですよ。
仕方なく、久々にスケッチブックを開く。真っ白い用紙をどんなに眺めても、真っ白い。不毛な私の中学生活と一緒だ。
中学生活……恋とか、部活とか?文化部で応援した野球部の試合が蘇る。私に気づいてマウンドから手を振ってくれたユニフォーム姿のクラスメイトが妙に格好良かった。あの悔し泣きは三年間頑張った証で、頭を下げた彼らの泥だらけのスパイクが印象的だった。 部活、描いてみようかな。私のしなかった青春を。本当はしたかった青春を。
バレー部のアタック、陸上部の高飛び、テニス部がラケットを振って、サッカー部がシュートを決める。様々な部活を見て回り、スポーツ関連の図書も参考にして鉛筆で描いていく。絵の中心部は決まっていた。
「野球のスパイクを一週間貸してくれない?」
頼んだ相手は、あの時私に手を振ってくれたクラスメイト、の隣にいた、ずっと好きだった人。緊張で声を上ずらせて、心臓を爆つかせて、中学生活最大の勇気を出した。彼の真っ黒なスパイクを家に持ち帰り、ちょっとニヤけつつ、泥、汚れ、ほつれのすみずみまで丁寧に再現した。
刷り上がった文集の冊子に、感動してしまった。鉛筆の風合いが白黒印刷に生きている。薄橙色の表紙ぴったりに縮小して印刷されると、スケッチブックの原版とは別物に見えた。つんと印刷したての匂いがした。
「この中学校が続く限り職員室に保管されるんだよ。君は一世一代の大仕事をやり遂げたね」
先生の大げさな言葉が嬉しかった。
あれから二十数年。年季の入った文集の表紙には、甘酸っぱくて気恥ずかしい、私の青い春が今でもくっきり刷られている。
コンビニのコピー機にUSBを差し込み、自宅にあるパソコンデータが印刷されていくのを眺めながら、なんと便利な時代なのかと感無量になる。
遠いあの日を思い出す。小学三年で転校し教科書はすぐ手に入ったが、算数のドリルがない。教室では隣の席の子と一緒に見せてもらい、宿題が出た時は近所の同級生ツヤちゃんの家に行き一緒に机に向かった。子供心にも気を遣うことだったが、ドリルが届くまでは我慢するしかなかった。
ある晩のこと、目が醒めると、母が卓袱台に向かって何やら作業している様子だった。こんな時間に何をしているのだろう。母は、私がそばまで行った時初めて気付いて顔を上げた。ペンを握り、傍らにはインク瓶とツヤちゃんのドリルが。そしてドリルと同じサイズに揃えた紙に計算問題を書き写していた。「もうすぐ終わる。明日からこれを持っていきなさい。ドリルはツヤちゃんに返してね。これでもう見せてもらわなくてすむわ」
母が笑顔を見せた。一ページに何十行も並んだ計算式。足し算、引き算、掛け算、割り算。二百ページ位あったろうか。母は夜を徹して一晩で書き写してくれたのだった。最後に画用紙で表紙を作り紐で綴じてくれた。美しい手作りドリルの完成だった。
翌日、担任の先生が算数の時間にドリルに驚き、声を張り上げた。「皆見てご覧、山本さんのお母さんが書き写して作ったドリルです。なんと素晴らしいお母さんでしょう」。先生は母の手作りドリルを高々と掲げて見せ、母を讃えたのだった。あの時の嬉しさと恥ずかしさと誇らしい気持ち。思い出すと目頭が今も熱くなる。ドリルが出来上がった時どんなに嬉しく母に感謝したことだろう。
家でも外でも容易に印刷できる便利な時代になった。書き写すしか方法がなかった時代に味わった私と母の小さな物語。幸せに膨らんだ心を大事に抱えて大人になった。 さ、印刷が終わった。九十歳の母が待つ家に帰ろう。
遠いあの日を思い出す。小学三年で転校し教科書はすぐ手に入ったが、算数のドリルがない。教室では隣の席の子と一緒に見せてもらい、宿題が出た時は近所の同級生ツヤちゃんの家に行き一緒に机に向かった。子供心にも気を遣うことだったが、ドリルが届くまでは我慢するしかなかった。
ある晩のこと、目が醒めると、母が卓袱台に向かって何やら作業している様子だった。こんな時間に何をしているのだろう。母は、私がそばまで行った時初めて気付いて顔を上げた。ペンを握り、傍らにはインク瓶とツヤちゃんのドリルが。そしてドリルと同じサイズに揃えた紙に計算問題を書き写していた。「もうすぐ終わる。明日からこれを持っていきなさい。ドリルはツヤちゃんに返してね。これでもう見せてもらわなくてすむわ」
母が笑顔を見せた。一ページに何十行も並んだ計算式。足し算、引き算、掛け算、割り算。二百ページ位あったろうか。母は夜を徹して一晩で書き写してくれたのだった。最後に画用紙で表紙を作り紐で綴じてくれた。美しい手作りドリルの完成だった。
翌日、担任の先生が算数の時間にドリルに驚き、声を張り上げた。「皆見てご覧、山本さんのお母さんが書き写して作ったドリルです。なんと素晴らしいお母さんでしょう」。先生は母の手作りドリルを高々と掲げて見せ、母を讃えたのだった。あの時の嬉しさと恥ずかしさと誇らしい気持ち。思い出すと目頭が今も熱くなる。ドリルが出来上がった時どんなに嬉しく母に感謝したことだろう。
家でも外でも容易に印刷できる便利な時代になった。書き写すしか方法がなかった時代に味わった私と母の小さな物語。幸せに膨らんだ心を大事に抱えて大人になった。 さ、印刷が終わった。九十歳の母が待つ家に帰ろう。
school
小学生の部
新聞の小さな切り抜きに、ありがとうを言う日が来るなんて。それは、しわくちゃで、インクがかすかに香る小さな切り抜き。その切り抜きの中で笑うぼくを、祖父はいつも財布に入れてお守りのように持ち歩いていた。
切り抜きは、ぼくがある作文コンクールで賞を取り、文章と顔写真付きで新聞になった時のものだ。ぼく以上に喜んだ祖父は、町の友人や至る所でその切り抜きを見せたようだった。輝く宝物を見せるかのように嬉しそうだったとたくさんの方に声をかけられ、祖父の歩いた道のりがわかるくらいだった。
今年に入り、祖父の財布はその宝物をしまったまま眠りについた。もう開く事はない。ぼくは、小さな切り抜きが誰かの喜びになる事を知った。出会いをつなぐ事を知った。宝物になる事を知った。ぼくは、あのしわくちゃの小さな切り抜きにありがとうと祈る。きっと、空の上でも輝いているだろう。
切り抜きは、ぼくがある作文コンクールで賞を取り、文章と顔写真付きで新聞になった時のものだ。ぼく以上に喜んだ祖父は、町の友人や至る所でその切り抜きを見せたようだった。輝く宝物を見せるかのように嬉しそうだったとたくさんの方に声をかけられ、祖父の歩いた道のりがわかるくらいだった。
今年に入り、祖父の財布はその宝物をしまったまま眠りについた。もう開く事はない。ぼくは、小さな切り抜きが誰かの喜びになる事を知った。出会いをつなぐ事を知った。宝物になる事を知った。ぼくは、あのしわくちゃの小さな切り抜きにありがとうと祈る。きっと、空の上でも輝いているだろう。
買ってきたばかりの本。ずっと読みたかった物語の続き。
本を手に取ると、ずっしりと重い。新しい紙の角のとがった感じを確かめる。表紙の絵にわくわくしながら本を開く。刷りたてのインクのにおいが心地よい。早く読みたい気持ちと、手の中にある安心感。
私は小さいころから本を読むのが大好きで、母に沢山の本を買ってもらった。本を開くたびに新しい世界へ入りこむことができる。主人公の仲間になった気分で、一緒にぼうけんに出かけたり、こわい場面で一しゅん本をとじ、落ちついてから、また本を開く。物語はかわらずいつもそこにある。母に怒られた時や弟とけんかした時も、本を開き、ぼうけんの続きをはじめると、安心してねむることができる。
どんな時にも私を支えてくれる本が大好きだ。本を読む楽しみをいつまでも持ち続けていたい。本を開いて、今日も新しいぼうけんに出かけよう!
本を手に取ると、ずっしりと重い。新しい紙の角のとがった感じを確かめる。表紙の絵にわくわくしながら本を開く。刷りたてのインクのにおいが心地よい。早く読みたい気持ちと、手の中にある安心感。
私は小さいころから本を読むのが大好きで、母に沢山の本を買ってもらった。本を開くたびに新しい世界へ入りこむことができる。主人公の仲間になった気分で、一緒にぼうけんに出かけたり、こわい場面で一しゅん本をとじ、落ちついてから、また本を開く。物語はかわらずいつもそこにある。母に怒られた時や弟とけんかした時も、本を開き、ぼうけんの続きをはじめると、安心してねむることができる。
どんな時にも私を支えてくれる本が大好きだ。本を読む楽しみをいつまでも持ち続けていたい。本を開いて、今日も新しいぼうけんに出かけよう!
「色」それはとってもすばらしいものです。赤色、青色、黄色、きみどり、そして黒。いろんな色があります。そして、それぞれの色を見ていろんな気持ちになります。わたしだったら、赤色などを見ると明るい気持ちになります。青色などを見るとさわやかな気持ちになります。みんなそれぞれの色にいろんな思いがあると思います。
この世界はたくさんの色であふれています。そして、わたしの身のまわりにはたくさんの印さつ物があります。
わたしは色えんぴつで描かれた旅の絵本を持っています。その本は見ているだけでそこに行っていたかのように楽しくなります。作者の目を通して見たものや感じたことが印さつ物となってわたしたちに届いているのだと思うのです。そう考えると「色」と「印さつ」はとってもすばらしい物だと思います。
この世界はたくさんの色であふれています。そして、わたしの身のまわりにはたくさんの印さつ物があります。
わたしは色えんぴつで描かれた旅の絵本を持っています。その本は見ているだけでそこに行っていたかのように楽しくなります。作者の目を通して見たものや感じたことが印さつ物となってわたしたちに届いているのだと思うのです。そう考えると「色」と「印さつ」はとってもすばらしい物だと思います。
私は、一年生の時から家族と四十七都道府県を一県ずつ巡り、人や地域文化に触れ、日本の良いところを見つける旅をしています。旅先から必ず持ち帰るものは、パンフレットやチケットです。それには、その土地の観光案内や歴史、名物が写真やかわいいイラスト入りでのっていて、旅先での思い出が鮮やかによみがえります。
一番印象に残っている県は福島県です。いわき市の「アクアマリンふくしま」のパンフレットを開くと、「潮目の海」の展示が美しく魚が生き生きとしていたことや、港の近くのレストランで祖父と食べた海鮮丼を思い出します。市内は、私が想像していた以上に復興が進んでいて、新しい家や道路がつくられ、福島県はがんばっているなと感じました。
パンフレットは私にとって、旅先での感動を呼び起こす「魔法のつえ」です。これから出かける二十二県では、どんな素敵なパンフレットに出会えるのか、ワクワクしています。
一番印象に残っている県は福島県です。いわき市の「アクアマリンふくしま」のパンフレットを開くと、「潮目の海」の展示が美しく魚が生き生きとしていたことや、港の近くのレストランで祖父と食べた海鮮丼を思い出します。市内は、私が想像していた以上に復興が進んでいて、新しい家や道路がつくられ、福島県はがんばっているなと感じました。
パンフレットは私にとって、旅先での感動を呼び起こす「魔法のつえ」です。これから出かける二十二県では、どんな素敵なパンフレットに出会えるのか、ワクワクしています。
今の時代、インターネットで本を読んだりする人も多いと思う。もうほとんど印刷物は使わないっていう人もいるかもしれない。でも、私は紙に印刷された本を一生読み続けたい。
なぜなら、紙は木からできている。本を開けたら、自然の木の臭いが私を包む。一つ一つていねいに印刷された一枚一枚のページ。作者が書いたちょっと変わった人の絵。その一さつの本は、この世界に一つしかない自分だけの特別な本なのだ。 でも、インターネットで読む本は、みんな同じ。だから私は紙に印刷された本を読みたい。
今の時代インターネットは確かに便利だ。けれど、本は自分一人の物で自分だけの世界を作ってくれる。自分の中でいくらでも想像力を広げてくれる。それは印刷のおかげだ。 私たちは、そういう印刷時代を生きている。
なぜなら、紙は木からできている。本を開けたら、自然の木の臭いが私を包む。一つ一つていねいに印刷された一枚一枚のページ。作者が書いたちょっと変わった人の絵。その一さつの本は、この世界に一つしかない自分だけの特別な本なのだ。 でも、インターネットで読む本は、みんな同じ。だから私は紙に印刷された本を読みたい。
今の時代インターネットは確かに便利だ。けれど、本は自分一人の物で自分だけの世界を作ってくれる。自分の中でいくらでも想像力を広げてくれる。それは印刷のおかげだ。 私たちは、そういう印刷時代を生きている。
「ゆいとくん、こうほうしにのってたよ」と、ともだちがいった。おかあさんにはなしたら、「空手のしあいのときにみんなでうつったしゃしんだよ。三いいないに入ったら、しょうじょうももらえるし、名まえものるからがんばりなさい」と、いった。ぼくは、ともだちが、みつけてくれたことがうれしくて、もっと、れんしゅうをがんばろうとおもった。
そして、ぼくのおかあさんは、いんさつがいしゃで、チラシのねだんや文字に、まちがいがないかチェックする校正といしごとをしている。「ママは、どうして校正のしごとをしているの?」と、きいたら「目に見えなくてもだれかのやくにたつしごとや目に見えなくてもだれかがしなくちゃいけないしごとが、よの中にはたくさんあるんだよ」といった。ぼくは、いみがわからなかった。でも、もう少し大人になったらわかるのかもしれない。
そして、ぼくのおかあさんは、いんさつがいしゃで、チラシのねだんや文字に、まちがいがないかチェックする校正といしごとをしている。「ママは、どうして校正のしごとをしているの?」と、きいたら「目に見えなくてもだれかのやくにたつしごとや目に見えなくてもだれかがしなくちゃいけないしごとが、よの中にはたくさんあるんだよ」といった。ぼくは、いみがわからなかった。でも、もう少し大人になったらわかるのかもしれない。
おふろのときにたくさんならんだボトルを見て、もし「シャンプー」といんさつされていないと、ほかのものとくべつがつかなくてこまるだろうとおもいました。もしいんさつがないと、どうなるでしょうか。おかしをかうときに何が中に入っているかわからなかったり、大すきな本も読めません。
いんさつがないとふべんで、さみしいかんじがします。わたしのまわりには、たくさんのいんさつされたものがあります。いんさつは生活をべんりにしてくれたり、楽しくしてくれたり、オシャレにもしてくれます。だからこれからもいんさつで、もっともっとかわいくて、楽しくあかるいみらいをつくっていってほしいです。
いんさつがないとふべんで、さみしいかんじがします。わたしのまわりには、たくさんのいんさつされたものがあります。いんさつは生活をべんりにしてくれたり、楽しくしてくれたり、オシャレにもしてくれます。だからこれからもいんさつで、もっともっとかわいくて、楽しくあかるいみらいをつくっていってほしいです。
わたしは、デンマークで生まれて、三さいの時に日本にひっこしてきました。なので、デンマークの絵本と日本の絵本を見て読んでそだちました。
今でもたまにデンマークの絵本をお父さんがデンマーク語をわすれないようにと読んでくれます。そうすると、デンマークのことを思い出してなつかしい気もちになります。おなじお話でも、絵がちがいます。
しょうらい、わたしの子どもに読ませてあげたいので、日本の絵本と、デンマークの絵本をたいせつにとっておきたいです。
今でもたまにデンマークの絵本をお父さんがデンマーク語をわすれないようにと読んでくれます。そうすると、デンマークのことを思い出してなつかしい気もちになります。おなじお話でも、絵がちがいます。
しょうらい、わたしの子どもに読ませてあげたいので、日本の絵本と、デンマークの絵本をたいせつにとっておきたいです。
わたしのお母ちゃんは、物語を書く人になろうとがんばっています。でも、コンクールに何回おうぼしても、いつも落とされています。失ぱいの連ぞくです。でもお母ちゃんは、「何回落ちても書くのが楽しいからいいの」と言って毎日書きつづけています。
お母ちゃんの物語には、わたしが登場します。もしお母ちゃんの作品が賞に入ったら、その物語がいんさつされて本になります。
原稿用紙に書かれたままだと家族しか読めません。でも、本になったら本屋さんや図書かんにおかれて、多くの人が、読むことができます。わたしが一番すきなお母ちゃんの物語は、わたしが自てん車にのって走っていたら動物たちと会ってだんだん友だちになっていく話です。とても楽しいお話なのでその話を多くの人に読んでほしいです。わたしは、早くお母ちゃんの作品がいんさつされた本を友だちとなかよくいっしょに読みたいです。
お母ちゃんの物語には、わたしが登場します。もしお母ちゃんの作品が賞に入ったら、その物語がいんさつされて本になります。
原稿用紙に書かれたままだと家族しか読めません。でも、本になったら本屋さんや図書かんにおかれて、多くの人が、読むことができます。わたしが一番すきなお母ちゃんの物語は、わたしが自てん車にのって走っていたら動物たちと会ってだんだん友だちになっていく話です。とても楽しいお話なのでその話を多くの人に読んでほしいです。わたしは、早くお母ちゃんの作品がいんさつされた本を友だちとなかよくいっしょに読みたいです。
学校の授業で版画をやった時、ぼくは、楽しくて夢中になり時間がすぎるのがとても速く感じました。彫った所は色がつかず、彫ってない所だけに色がつくというのが面白くて好きになりました。後で少し調べた所、昔、多くの人に正確に伝える目的から文字版画が出来、技術が進歩して印刷と版画に大きく分かれていったという事が分かりました。
今では技術がどんどん進化していき、ペーパーレス化が進んでいるけれど、コンピューターの中やメールなど、キー押し一つで全て消されてしまう時代なので、次の世代に正確に伝える事が出来るのか、不安になりました。実際にぼくが大好きだったゲームのデータをボタン一つで全て無くしてしまったのです。
ぼくは、目に見えてさわれる紙を大事にしたいです。
今では技術がどんどん進化していき、ペーパーレス化が進んでいるけれど、コンピューターの中やメールなど、キー押し一つで全て消されてしまう時代なので、次の世代に正確に伝える事が出来るのか、不安になりました。実際にぼくが大好きだったゲームのデータをボタン一つで全て無くしてしまったのです。
ぼくは、目に見えてさわれる紙を大事にしたいです。
ぼくは、いんさつのすごいところを考えてみました。まずまんがや教科書など同じ物をたくさん作ることができます。次にシールにしてバスや電車などいろんな形の物にいんさつできます。また、お札はまねができないようなまほうのいんさつをしています。レジぶくろや紙ぶくろや名しなど、名前をおぼえてもらえるようにするいんさつもあります。
いろいろなすごいところがあってびっくりしました。
そして、思い出や楽しかった写真を本にして大人になってものこせるようにできるということも思いつきました。このあとも楽しいことがたくさんあるといいなぁと思います。そう考えているとわくわくしてきました。
いんさつはぼくをしあわせな気持ちにしてくれてすごいと思います。
いろいろなすごいところがあってびっくりしました。
そして、思い出や楽しかった写真を本にして大人になってものこせるようにできるということも思いつきました。このあとも楽しいことがたくさんあるといいなぁと思います。そう考えているとわくわくしてきました。
いんさつはぼくをしあわせな気持ちにしてくれてすごいと思います。
「何か買っていいよ」
買いものに行った時に、そう言われたらいつもカードがおまけについたチョコレートを買います。ようちえんの時は、かめんライダーのカードを買っていました。小学生になった今は、ポケモンのカードが入ったものを買います。キラキラしたものが当たるとうれしいです。ふくろを開けると、かめんライダーのチョコレートもポケモンのチョコレートも大きさはほとんどおなじです。カードの大きさもおなじです。とうめいのふくろに入っておみせで売っていたら、どれがどれかわかりません。ふくろにいろんないんさつがあるからまちがえずに買うことができるんだと思いました。買って開けたらすててしまうものだけれど、まちがえずに買いたいものが買えるのは、いんさつのおかげです。いんさつしている人たちにありがとうと言いたいです。
買いものに行った時に、そう言われたらいつもカードがおまけについたチョコレートを買います。ようちえんの時は、かめんライダーのカードを買っていました。小学生になった今は、ポケモンのカードが入ったものを買います。キラキラしたものが当たるとうれしいです。ふくろを開けると、かめんライダーのチョコレートもポケモンのチョコレートも大きさはほとんどおなじです。カードの大きさもおなじです。とうめいのふくろに入っておみせで売っていたら、どれがどれかわかりません。ふくろにいろんないんさつがあるからまちがえずに買うことができるんだと思いました。買って開けたらすててしまうものだけれど、まちがえずに買いたいものが買えるのは、いんさつのおかげです。いんさつしている人たちにありがとうと言いたいです。
一枚の印刷された名刺から、私の物語ははじまった。
「お母さん、子供ホスピスって何?」
母の名刺入れからチラッと見えた名刺にそう書かれていた。なぜかその言葉に強くひかれ、思わず聞いてしまった。
母はおだやかな死を迎えるためのホスピス病棟で働いていたので、色々なことを教えてくれた。そこで私は、髪を寄付するヘアドネーションに出会った。
私は、毎朝母にかわいく髪の毛をセットしてもらうのが楽しみで、五年近く髪を伸ばしている。自まんの長い髪。
迷いはなかった。三十センチばっさり切って髪の毛を寄付した。人の役に立てることが、こんなにも気持ちの良いものなのか。私の髪も心も、体全部がばんざいをして喜んでいる。
一枚の名刺からはじまった私の幸せな物語。今度は私の寄付した髪と出会った人が、ハッピーエンドになることを願っている。
「お母さん、子供ホスピスって何?」
母の名刺入れからチラッと見えた名刺にそう書かれていた。なぜかその言葉に強くひかれ、思わず聞いてしまった。
母はおだやかな死を迎えるためのホスピス病棟で働いていたので、色々なことを教えてくれた。そこで私は、髪を寄付するヘアドネーションに出会った。
私は、毎朝母にかわいく髪の毛をセットしてもらうのが楽しみで、五年近く髪を伸ばしている。自まんの長い髪。
迷いはなかった。三十センチばっさり切って髪の毛を寄付した。人の役に立てることが、こんなにも気持ちの良いものなのか。私の髪も心も、体全部がばんざいをして喜んでいる。
一枚の名刺からはじまった私の幸せな物語。今度は私の寄付した髪と出会った人が、ハッピーエンドになることを願っている。
認定状況
GPマークの仕組み
 ❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)
❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp